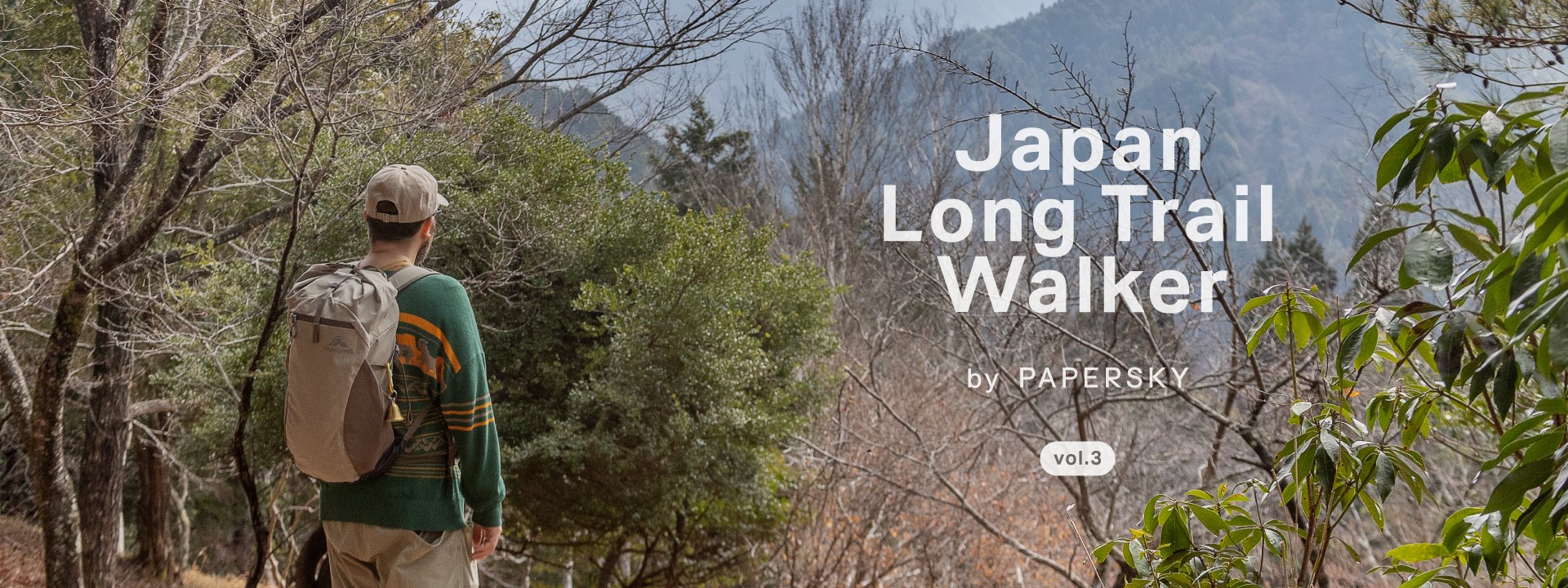江戸時代に整備された因幡街道は、播磨国(兵庫県)姫路城下と因幡国(鳥取県)鳥取城下を結んだ脇街道のひとつ。なかでも志戸坂峠を超える智頭往来は鳥取藩の参勤交代に用いられ、街道沿いに置かれた平福宿(兵庫県佐用町 )、大原宿(岡山県美作市)、智頭宿(鳥取県智頭町)といった宿場町は大いに賑わったとか。ここでご紹介するのは、坂根宿(岡山県西粟倉村)を中心とした智頭往来の歩くハイキングストーリー。武士や商人が行き来した江戸時代に思いを馳せ、宮本武蔵ゆかりの旧道を歩く。


脇街道として整備された江戸時代以前から、交通の要路として栄えたという因幡街道。参勤交代の道となった以降は本陣・脇本陣・問屋を備えた宿場町も置かれ、なかでも“因幡街道三宿場町”とされた平福宿、大原宿、智頭宿は政治・経済・文化の中心として栄えたそうだ。


宮本武蔵と、修験の山と
剣豪・宮本武蔵の故郷として知られる智頭急行宮本武蔵駅で下車。まずは生家跡や墓、武蔵を祀った武蔵神社などが置かれた「武蔵の里」を散策する。「武蔵の里」から因幡街道を大原宿方面へ。大原町の中心部には数寄屋造りの御成門を要する本陣や脇本陣、明治18年に創業した田中酒造場など、なまこ壁や出桁を設けた家々が連なり、古い街並みの風情に旅情がそそられる。宿場町から因幡街道をさらに北上し、鳥取方面へ向かう。大原町のとなり、旧東粟倉村からは岡山県最高峰の後山(うしろやま)と、それに連なる「氷ノ山(ひょうのせん)・後山・那岐山(なぎさん)国定公園」の一部の山々がよく見えた。標高1344mの後山はかつての修験の場で、その修験場は現在も厳格な女人禁制が守られているとか。中腹から山頂にかけて美しいブナの天然林が広がっている、通称「美作アルプス」(駒の尾山・鍋ヶ谷山・船木山・後山)を縦走するコースが地元ハイカーに人気だそう。
山間の村になぜ!?ユニークなベンチャーが集まるワケ

東粟倉村の先に現れるのが、“最先端の田舎”と呼ばれる西粟倉村。かつて坂根宿が置かれていたエリアだ。人口1300人弱の西粟倉村は、総面積の約95%が山林、その内の約85%をスギ・ヒノキなどの人工林が占めており、地元産の木材や森林を活用する「百年の森林(もり)構想」と、そこから派生する起業型人材育成を掲げたユニークなまちづくりを進めている。



西粟倉村から先は、村内に暮らすアメリカ人の岸田パトリックさんが案内役を買って出てくれた。パトリックさんは現在、母国でのトレイルビルドの経験を生かし、妻の萌さんとともに立ち上げたTatara Trailsにて、地元の山林を活用したマウンテンバイクトレイルの整備やライドツアーの企画などを行っている。「森の価値を高めるためには、さまざまな人に森に入ってもらい、体験や遊びを通じて森や山に親しんでもらうことが必要です。私たちは多彩なアクティビティでそのお手伝いをしていきます」とパトリックさん。街道から外れて案内してくれた村南西部の山林はスギ6割・ヒノキ4割の人工林。ここから切り出された材は家具や木製品、建材などに利用されている。


こうした木材のショウケースとして機能しているのが、街道沿いに建つ美しい木造建築物、あわくら会館だ。村内のスギ・ヒノキ材を97パーセント使用したこちらは、粟倉村の役場と図書館、生涯学習の機能を合わせた複合施設。外装もさることながら、無垢材をふんだんに活用した内装も見ものだ。こちらの内装は、村内のスギ・ヒノキで家具をつくるようびや、木薫、工房kodamaといったローカルの作り手が担っているそう。BASE101% -NISHIAWAKURA-、あわくら会館、あわくら温泉元湯といったユニークな施設を通過すると、やがて村の最北部にある志戸坂峠に至る。


播磨と因幡の国境にあるこの峠道、山越ルートとしての歴史は古く、遡れば『日本書紀』や『播磨国風土記』にも登場している。牛馬が通らないほど険しく、冬季の雪も深いことから古くから難所として知られたが、山陰地方に暮らす人々が中国山地を越えるためにはここを通らざるを得なかったようだ。江戸時代になると鳥取藩の参勤交代に用いられるようになり、鳥取藩主の池田家がこれを整備。幕末にはなんと、1,172名の大所帯で峠を越えたという記録がある。現在の峠道は明治18年、国道22号に指定された際に整備されたもので、農林業や生活のための道路として使用されながら、地元住民による維持・保存活動が行われてきた。よく手入れされた登山道には昔の石垣や茶屋跡がそのまま残っている。「展望台」の標識に導かれた先には、広葉樹の林が広がっていた。



今回は志戸坂峠をゴールとしたけれど、時間があれば智頭側に下ってもよさそうだ。因幡街道から少し外れるけれど、西粟倉村の人工林とはまったく異なる風景や自然の営みを感じられる「若杉原生林」もぜひ歩いてみたいところ。村の北東部に位置する「若杉原生林」は、ブナやカエデ、ミズナラなどさまざまな雑木が織りなす中国地方屈指の森林で、3km・5kmのハイキングコースを歩きながら吉野川の源流のせせらぎやアカゲラなどさまざまな鳥の声を楽しめるとか。
長期のバックパッキングから街道歩きまで

トレイルあり、林道あり、宿場町での道草あり……と、めまぐるしくロケーションが変化する街道歩き。チョイスしたのは、macpacの新作バックパック「マカナウ」だ。耐久性と軽量さのバランスが秀逸なAzTec®︎6oz素材を用いたこのモデルはロールトップオープニングが特徴的。荷物の容量に合わせて自在に拡張できるから、オールシーズンで重宝しそう。




使い込むほどに味が出て、体にしっくりと馴染んでくるAzTec®︎。経年変化を楽しめるバックパックを相棒に、日本の旧道歩きを楽しんでみよう。

【今回使用しているアイテム】
Manakau 35 (color : LD)
Manakau 22 (color : RC)
Trek Shoulder S(color : LD)
Trek Shoulder S(color : RC)
〈PAPERSKY〉Japan Long Trail Walker PAPERSKYバージョンはこちらから